和音が入っていて、音がきれいに混じり合っているような部分は、バイオリンで演奏するのに技術がいるところです。
気持ちよく弾きたい時には、本当のところは、
「なるべく和音が出てこないでほしいなー」と思います。
和音が出て来たりすると、曲が盛り上がり、カッコよく聞こえるので、この技術を習得できたら、本当に素晴らしいです。
フィギュアスケートで例えてみると、
難しいジャンプやステップのような、みんなが見て盛り上がるところですが、演技する方としては、簡単にはできないので難しい部分になります。
うまくできれば、とても達成感があることでしょう。
今回は、バイオリンで弾く和音についてまとめたいと思います。
和音を弾くには
⑴ 弓の扱い方
弓を使って、二本の弦を同時に鳴らすのには、技術が必要です。
それは、一本の弦だけに弓を当てて弾くよりも難しいです。
① 2本の弦にちょうどよく当たるように鳴らす弓の角度に、より正確さが求められます。
② また、弓にかける圧の調節がうまくいかないと、キーッという上ずったような音になっってしまいます。
時間差を利用して、最初に鳴らした弦の音がまだ残っているうちに、次の弦も2本ずつ鳴らすと、3本の弦、4本の弦を同時に鳴らす和音を弾くこともできます。
うまく鳴らすことができれば、音の幅とボリュームが広がり、カッコよくなります。
曲の終わりなどに、ジャンッ!とかジャーン!と終わる時に和音が出てくるときがあります。
ここでしっかり音が出せると、気持ちが良いです。
⑵ 音程をとる

和音になると、同時に二つ以上の音の音程を正確に取る必要があります。
同時に鳴らせるのは、2本の弦までなのですが、2本ずつ弾いてずらすと、3本の弦、4本の弦の音を同時に出して和音を弾くことができます。
その場合、音程を最大4つ同時にとることになります!!
開放弦で、押さえないで良い弦が混じっていると、だいぶ助かります。
弦を押さえるポイントの組み合わせが、左手の形を合わせるのが難しい時もあります。最初は指がつりそうだと思えるかもしれません。
また、隣の弦も一緒に同じ指で押さえることもあれば、隣の弦には触れないようにして押さえなければきれいな音にならないときもあるので、押さえ方も難しいです。
単音だけなら、音が外れてもまだちょっと外れているな、くらいで済みますが、和音で外れると、音がうまくかみ合わず、とても不快な音が出てしまいます。
一生懸命に弾いているのに、美しい音どころか、嫌な音がしてしまうのです。とてもリスクの大きなことです。
和音の音程がとれると、音がうまく合わさり、深みのある音楽になります。
聴き手も、「どうやって弾いているんだろう?」「すごいな〜」と言ってくれることでしょう。そうして、バイオリンが好きな人が増えていってくれたら嬉しいな、と思います。
※ 音程についての関連記事
【ベートーベンのクロイツェルソナタ】
ベートーベン作曲のクロイツェルソナタは、最初の出だしが美しい和音になっています。
この最初の部分を美しく弾けるだけでも、すごいな〜と思います。
ピアノとの掛け合いが素晴らしい曲です。
※ 合奏の関連記事
難易度に差がある
開放弦同士の2本だったり、
開放弦と押さえる弦1本
というように、開放弦が混じっていると弾きやすいです。
最後は、4本すべて指で押さえて、同時に鳴らすという、ものまであります。
また、和音が1回ではなく、しばらく続いて出てくると、さらに難しくなります。
そのパートは飛ばしてしまいたくなります。
上達するには、むしろそのパートのみを何度も練習する方が、時間を無駄にしない練習の仕方です。
練習の仕方
同時に二つ以上の音程を正確にとるには、一つずつに音程を正確に取ることから始まります。
それで、まずは左手の音程を取る練習をします。
同時におさえますが、1音ずつ鳴らします。
それから同時にも弾いてみます。
そして音が綺麗にはまっているかを確かめます。
この音の響きの違いをしっかり覚えていくのです。
まとめ
バイオリンの難所とも言える和音を、美しく弾けたら、かなり技術が上がっているはずです。
実際に練習してみると、どうしてもつっかえながら弾いている感じになってしまいがちです。
プロの演奏はすごいな〜、と思います。
※ バイオリンの技法の関連記事


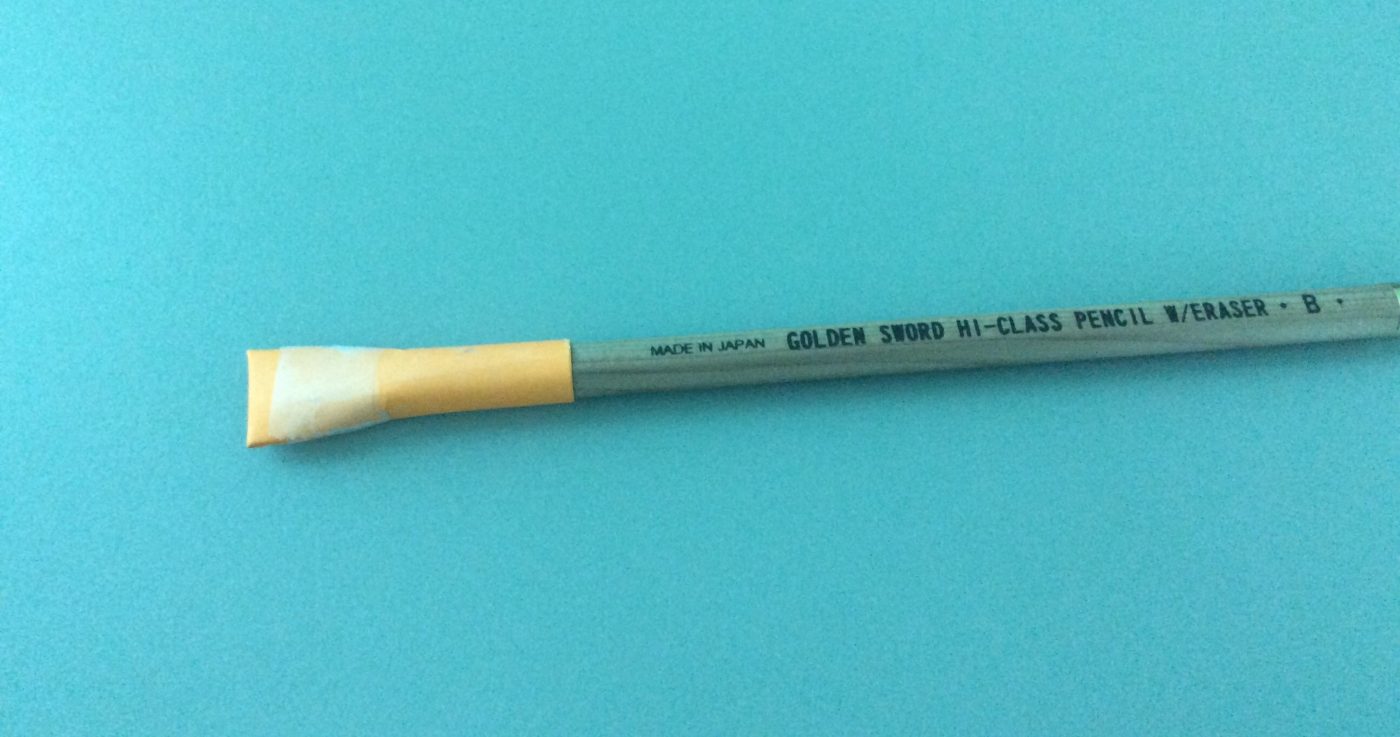



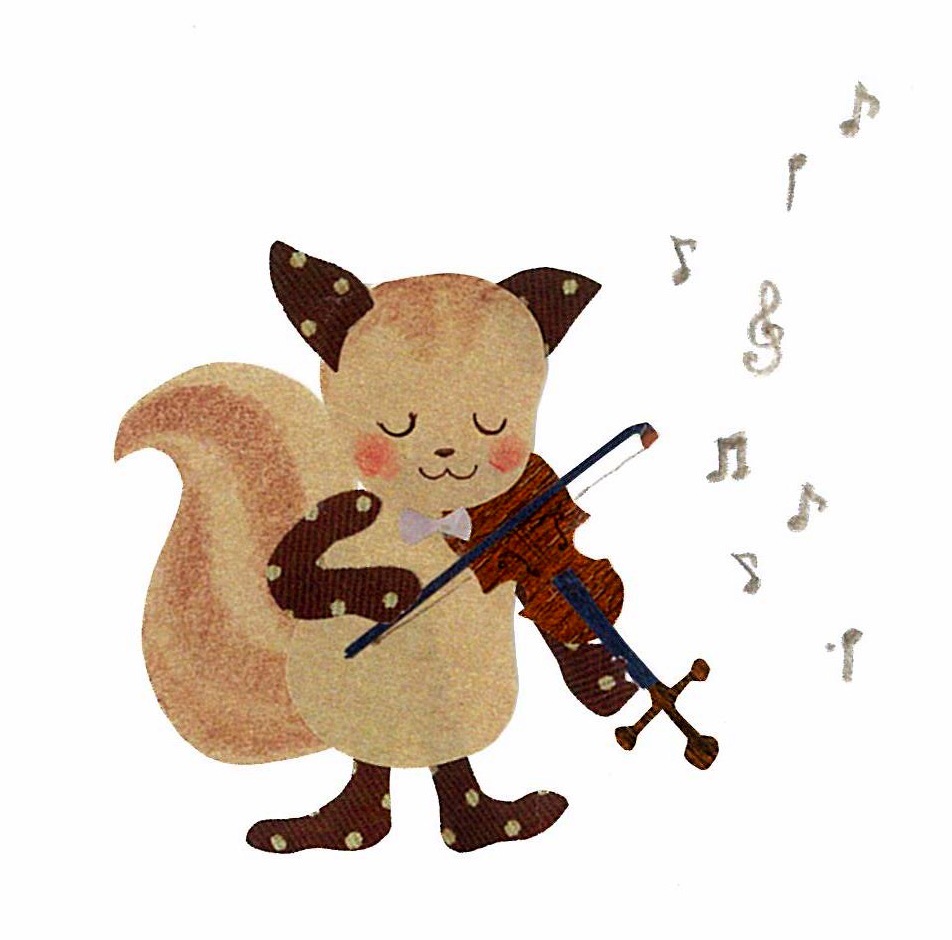

コメント